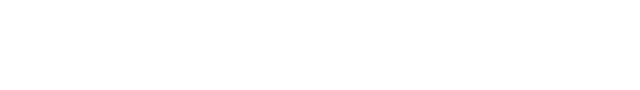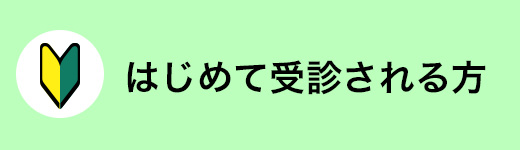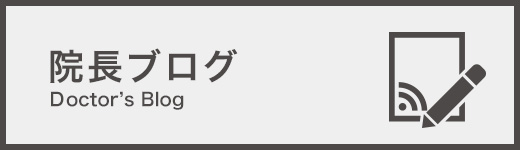生活習慣病
生活習慣病とは、「食習慣・運動習慣・休養・喫煙・飲酒等の生活習慣が、その発症や進行に関与する疾患」とされています。
生活習慣と関連する病気としては、高血圧・脂質異常症・心筋梗塞・狭心症・高尿酸血症・糖尿病・アルコール性肝疾患・がんなどがあり、多くは自覚症状のないまま進行していきます。
そのため、日ごろから特定健診をはじめとする各種健診を受けて体の変化を確認し、病気になる前に生活習慣を見直しましょう。
また、生活習慣は小児期に身につくことが多いため、生活習慣病を予防するためには子供の頃から食生活や運動に注意することが大切です。
日常生活の留意点について
食事:「減塩・適正カロリー・3食バランスよく」が基本
- 野菜摂取量350g/日以上
- 食塩摂取量:男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満
- 飽和脂肪酸:総エネルギーの7%未満目標
- 主食、主菜、副菜をバランスよく
- 加工食品や外食に偏らないように
喫煙:生活習慣病の最大のリスク因子
- タバコに含まれる有害物質が血管内皮を損傷し慢性炎症と動脈硬化を促進
- 受動喫煙でも心疾患・脳卒中のリスクが増加
- 禁煙支援外来の活用を推奨
飲酒:適度の飲酒と休肝日を意識
- アルコール量≦20g/日(目安;ビール中瓶1本、日本酒1合、ワイン180?)
体重:内臓脂肪型肥満の予防が重要
- 適正体重はBMI18.5~24.9
- 腹囲の管理を重視(男性<85㎝、女性<90cm)
運動:1日60分の身体活動を目標
- ウォーキング、ストレッチなど無理なく継続できる運動を
睡眠:質の高い睡眠がホルモンと自律神経を整える
- 成人の理想的な睡眠時間は6~8時間
- 就寝・起床時間を一定に保つ
- 寝る前のスマホ・カフェイン・アルコールを控える
- 朝日を浴びて体内時計をリセットする
主な生活習慣病
- がん
- 心疾患
- 脳血管疾患
- 糖尿病
- 高血圧性疾患
- 肝硬変
- 慢性腎臓病
- 脂質異常症
- 肥満症
糖尿病
糖尿病は、インスリンの機能が十分に働かないために、血液中のブドウ糖が増えてしまう病気です。
インスリンは膵臓から出るホルモンであり、血糖を一定の範囲に調節する働きを担っています。
糖尿病には、発症原因によりいくつかのタイプに分類されますが、日本ではその多くが2型糖尿病で、遺伝因子とともに生活習慣や外部要因等が関与して発症すると考えられています。
糖尿病は様々な合併症を起こします。
網膜症、腎症、神経障害、動脈硬化による脳卒中や心血管障害、下肢壊疽、歯周病などです。
放置していると症状が進行し、重篤になってしまうこともあります。
2型糖尿病の治療の基本は、食事療法と運動療法により適正に体重をコントロールし、インスリンの効果を上げることです。
食事療法と運動療法だけでは不十分な場合に、経口薬や注射薬による治療が必要となります。
高血圧
診察室での繰返し測定値で140/90mmHg以上、家庭血圧では135/85mmHg 以上の場合、高血圧と診断されます。
高血圧には、他の疾患が原因で起こる2次性高血圧と、原因のはっきりしない本態性高血圧があります。
日本人の高血圧の約9割は本態性高血圧で、遺伝的因子に加え、塩分の摂りすぎや肥満、過度の飲酒、運動不足、ストレス、喫煙などの生活習慣が関与すると考えられています。
高血圧の状態が続くと、以下のような合併症をきたします。
- 心不全
- 心筋梗塞・狭心症
- 脳出血・脳梗塞などの脳血管障害
- 眼底出血
- 高血圧性腎障害、腎不全
- 閉塞性動脈硬化症
定期的な健康診断や家庭での血圧測定により、早期に発見することが重要です。
また、高血圧を予防するために、日頃から生活習慣の改善に取り組みましょう。
- 減塩
- 禁煙
- 過度の飲酒を控える
- 十分な睡眠をとる
- ストレスをためない
- 肥満を解消する
- ストレッチや有酸素運動を継続する
生活習慣の見直しだけでは血圧コントロールが不十分な場合、薬物治療の適応となります。治療における降圧目標値については、75歳未満の場合、家庭血圧で125/75mmHg未満です。一方75歳以上の方では、家庭血圧135/ 85mmHg未満を目安としています。
また、糖尿病や慢性腎臓病を合併している場合の降圧目標値は、125/75mmHg未満とされていますが、心筋梗塞や脳卒中などを発症するリスクが高いことから、目標値が厳格に設定されているためです。
血圧について気になることがある時は、早めの受診をお勧めします。
脂質異常症
血液中の脂質には、コレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類があります。
これらのうち、LDL(悪玉)コレステロール、HDL(善玉)コレステロール、中性脂肪が基準値から外れた状態を、脂質異常症といいます。
診断基準(早朝空腹時)2012年動脈硬化ガイドラインより改変
| 高LDLコレステロール血症 | LDLコレステロール | 140mg/dL以上 |
|---|---|---|
| 境界型高LDLコレステロール血症 | 120-139mg/dL | |
| 低LDLコレステロール血症 | HDLコレステロール | 40mg/dL未満 |
| 高トリグリセライド血症 | 中性脂肪(トリグリセライド) | 150mg/dL以上 |
LDLコレステロールには肝臓に蓄えられたコレステロールを全身へ運ぶ作用があり、HDLコレステロールには余分なコレステロールを全身から回収し、肝臓へ戻す作用があります。
HDLコレステロールは動脈硬化を進行させないように働く一方で、LDLコレステロールは増えすぎると血管壁に蓄積してアテローム動脈硬化が進行します。
そのため、HDLコレステロールは「善玉コレステロール」、LDLコレステロールは「悪玉コレステロール」と呼ばれています。
脂質異常症の発症には、過食、運動不足、肥満、喫煙、アルコール多飲、ストレスなどが関係しているといわれています。
健康診断で脂質異常症を指摘されても自覚症状がないため放置していると、動脈硬化が進行し虚血性心疾患や脳血管障害などのリスクが高まります。
治療には、食事療法、運動療法、薬物療法があります。予防するためには、何よりも生活習慣の改善が重要です。
高尿酸血症
高尿酸血症とは、尿酸値(血液中にある尿酸の濃度)が7.0mg/dLを超えた状態をいいます。
高尿酸血症が続くと、血液中で飽和状態となった尿酸が結晶となって関節や腎臓に蓄積します。
関節に溜まった尿酸の結晶が痛風発作の原因となります。
痛風そのものは短期間で治まったとしても、体内の尿酸結晶はそのまま存在し続けます。
そのため、痛風発作が再発したり、腎臓内の尿酸血症が原因となり尿路結石や腎臓病を引き起こします。
また、高尿酸血症は、さまざまな生活習慣病(高血圧、心疾患、メタボリックシンドロームなど)のリスクを高め、動脈硬化を促進させると言われています。
健康診断や人間ドックで尿酸値が高いと指摘されたり、突然足の指の付け根に歩けない程の強い痛みが生じたときは、できるだけ早く受診しましょう。